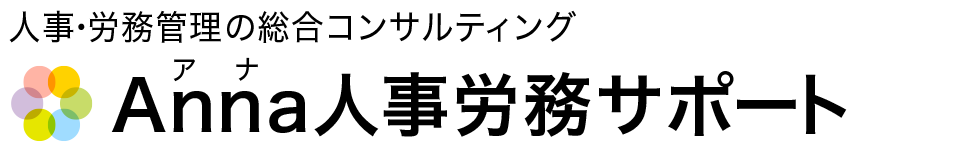Q&A 就業規則の手数料が高額なのはなぜですか?
“そろそろ社員も増えてきたことだし、就業規則を作ろうかな“と、ネットで社労士事務所を検索して就業規則の作成手数料を見てビックリする方も多いかもしれません。
大体の事務所が20万円~の手数料を表示しています。更に、顧問契約があるか、ないかでも額は変わります。
中には、数万円で作成する事務所や、50万円以上と提示している事務所もあります。
適正な相場というものがわからず、各社労士の言い値? と不信感を抱く方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、各社労士事務所が数万円~50万円以上の手数料を決めているのには、きちんと根拠があり、適当に決めているわけではありません(と個人的には思っています)。
低価格な就業規則と高額な就業規則はどこが違うのか?
低価格の就業規則の中身は法的に大丈夫なのだろうか? または高額な就業規則を作ればトラブルとは無縁でいられるのだろうか? という疑問もあるかと思います。
価格の違いには次のような理由があります(以下は、当方の考えるものであって、各社労士により考えに違いがあることを了承願います)。
まず、前提として、就業規則には必ず記載しなければならない、次の絶対的必要記載事項というものが労働基準法で定められています。社員を雇用する際に、最低限伝える必要がある事項です。
価格に関係なく、これらの項目は必ず記載されているはずです。
【絶対的必要記載事項】
✅労働時間に関する事項…始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
✅賃金に関する事項…賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
✅退職に関する事項…解雇の事由を含む退職に関する事項
低価格の就業規則…これら必要最低限の項目のみのテンプレートを作成し、依頼された会社の実態を当てはめて作成する、という形式の場合があります(簡易版の就業規則、と呼ぶこともあります)。
テンプレートがあれば、ヒアリング内容も決まったことを聞けばよいですので、作成にかける工数や時間が一定になり、価格を抑えることができる、ということです。
社員とのコミュニケーションが良くとれていて、トラブルもない、という会社の場合は、ルールを明確にする、という趣旨でこのような簡易版の就業規則でも良いと思います。
高額な就業規則…絶対的必要記載事項のほかに、次の相対的必要記載事項を追加したり、会社独自の規定をオリジナルで作成する場合は、価格が高くなっていきます(スタンダード版、オーダーメイド版など事務所により様々な名称を付けています)。
【相対的必要記載事項】
退職手当に関する事項、臨時の賃金等に関する事項、費用の負担に関する事項、安全衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償等に関する事項、表彰・制裁に関する事項、その他、事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項
就業規則が高額になる一番の理由
就業規則が高額な一番の理由は、作成する社労士が持つ経験と知識、これらをどの程度利用するか、によります。
就業規則を事務所の商品として販売するからには、作成したものに対する責任が発生します。ですので、どの社労士も相当な時間をかけて関連する法律の勉強をしています。それは、労働基準法だけにとどまらず、育児・介護休業法、高年齢者雇用安定法などなど、多岐にわたります。
また、社労士は、作成した就業規則の各制度が、実務の場面でどのように影響するか、などの実体験を蓄積しています。
就業規則を作る最初の段階で、依頼会社の労務管理の実態などのヒアリングを行いますが、そこで、それまでの経験と知識をフル稼働して、その会社に最適の就業規則はどのような形か、ということをイメージします。
ですので、ご依頼当初はなるべく費用のかからない簡易版をご希望されている場合でも、ヒアリングをしてみたら未払残業代があった、などという場合は、未払残業代を解消するための制度を入れる必要があり、価格が高くなってしまったりすることもあります。
また、リスク対応を気にされる場合には、非常に緻密な制度を作ることもありますが、そうすると価格は高くなっていきます。ですが、社員数がそれほど多くない会社で、ガチガチの就業規則を作っても、それを運用できない場合もありますので、そういうときは、少しランクを落とすことをお勧めする場合もあります。
以上のようなことを総合して、就業規則の価格は決まります。
当事務所の就業規則作成費用は、中小企業向けのものを前提とした目安です。実際にご依頼を頂いた場合には、まずヒアリングを行い、お見積りをさせていただきます。
詳しくは下記ページでご確認くださいませ。