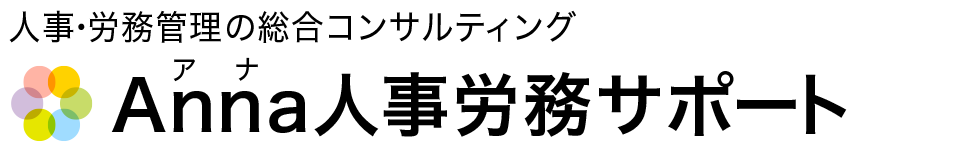年金事務所調査が厳しくなっている?
年金事務所の調査が厳しくなっている! という声が最近よく耳に入ってきます。
コロナ禍で企業経営が大変厳しくなっている状況でも、未納があった場合は厳格に最大過去2年に遡って適用、保険料を徴収されているようです。
加入要件を満たしている法人なのに社会保険の適用逃れをしていた場合は、いつかは加入しなければならない、という覚悟があるかもしれません。
が、うっかりミスで資格取得手続きや昇給・降給などの保険料変更手続きが漏れていた、という場合は、精神的(なぜ、きちんと確認しなかったのか~、という後悔)にも金銭的にも結構大きなダメージを受けます。
うっかりミスのように“故意”でない場合でも保険料を納めていないことに変わりありませんので、正しい手続きをし直して、未納の保険料を計算して納付する必要があります。
※社員からも未納の保険料を徴収する必要がありますが、会社のミスの場合、心理的には徴収しづらいかもしれません。降給の手続きをしていなかった場合は、社員から保険料を多く徴収していることになりますので、返金の手続きが必要です。
弊所では資格取得手続きの時には社員ごとの手続きマニュアルを作り、全てが終わるまで日々チェックしています。
昇給・降給の手続きは、給料計算が関係します。
弊所で給料計算を受託している場合、給料計算そのものにも大変神経を使いますが、この保険料の変更手続きの漏れにも大変神経を使っています。
毎月の給料が確定した時点で、月額変更予定リストに該当者を記入し、翌月の給料計算開始時には月額変更後の標準報酬を反映する社員がいないかをチェックしています。給与計算ソフトの集計でも対象者を表示する機能がありますが、ソフトだけを鵜呑みにしているとやはり漏れが生じることがありますので、自分の認識とソフトとを併用しています。
【随時改訂(月額変更)手続き】
・昇給・降給した(固定的賃金が変更となった)月から3ヶ月間の平均をとり、
・標準報酬月額が2等級以上増減し、
・3か月間の賃金支払い基礎日数が17日以上の場合に行うものです。
以下に調査の概要と日常業務で注意したい点を書いてみます。
■調査の概要
調査の種類には、主に、訪問調査、呼び出し・郵送調査、定時決定時調査などがあります。
どのような会社を調査対象とするのかについては、日本年金機構の「令和2年度計画」に詳しく記載されていますので、下記リンクをご参照ください。
【日本年金機構 令和2年度計画】
https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/disclosure/nendokeikaku.files/R02.pdf
■日常業務で注意したい点
1.資格取得
・手続きもれ…協会けんぽの場合は手続きをしていないと健康保険証が届かないため、一応の目安になると思います。
注意したいのは組合けんぽの場合です。健康保険と厚生年金の手続きを別々に行うので、健康保険証が届いたとしても、厚生年金の手続きが漏れている場合があります。
・パートなどの加入拒否…パートさんには、収入を配偶者の扶養の範囲内で抑えて働きたい、という方が多いです。と言いながら、通常の月は社会保険の加入基準を超える時間働き、年末になると労働時間を調整する、ということもあります。経営者としては社会保険の加入を勧めても、それを理由に退職されても困るので、強制できない場合がありますが、社会保険に加入したくないのであれば、基準を超えない労働契約を結んで、その通りに働いてもらうことが大切です。
・外国人労働者の加入拒否…外国人労働者の方も基準を満たす働き方をしているのであれば、当然社会保険に加入する必要があります。が、病気にかからないから健康保険はいらない、とか、将来は自国に帰るから年金を払いたくない、などの理由で加入を拒否する場合があります。
※第3号被保険者の手続きにも注意
保険料には関係ありませんが、資格取得時には、社員の配偶者の第3号被保険者の手続きも確実に行えているか確認が必要です。扶養の手続きをしても第3号手続きが漏れている場合があります。
2.給料の支給額に変動があったとき…この場合の“うっかり手続きもれ”が発生しやすいです。
報酬月額の変更手続きが必要になる場合
・昇給、降給など固定給が変わったとき
・時給単価や月給を変更したとき(最低賃金が変わった場合など)
・通勤手当が変わったとき(通勤手当も固定給です)
・パートさんが正社員になったとき(時給から月給など、給与体系が変わったとき)
・各種手当(役職手当、住宅手当など)の変更
・歩合給の単価、歩合率の変更
・その他
加入もれや手続き漏れの対象者が多い場合は、遡及される保険料も〇百万円、〇千万円と高額になることもあります。そうなると会社の経営に相当な影響が出ます。
とにかく日々の丁寧な仕事、チェックが重要です。